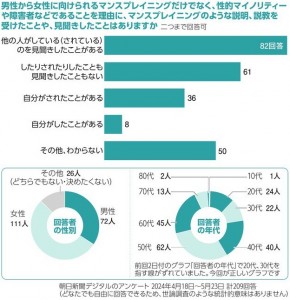マンスプレイニングとは、見下したような自信過剰な、そしてしばしば不正確な、または過度に単純化された方法で、女性や子どもに何かについてコメントしたり、説明したりすることを言います。この現象は、自信過剰と無知の組み合わせであるとされています。説明を受ける者が説明者よりも多くのことを知っているという事実を無視して説明すること、多くの場合男性が女性に行うことと定義されることから、Man‐splainingと呼ばれます。
英語圏では、マンスプレイニング以外の様々な○○スプレイニングもしばしば話題になります。障害を持たない人から持つ人へのエイブルスプレイニング、異性愛者がそれ以外の性的指向の持ち主に行うヘテロスプレイニングというのもあります。説教される構造を、当事者は分かっています。その構造を見ようとせず、気づかないのは常に説教する側です。自覚がないこともありますが、単に無知なだけでなく、無知でありたい面もあるのではないかと思います。
各種のスプレイニングが起こる構造には、認識的不正義という問題が関係しています。集団に偏見が存在することで、会話などによる知識の共有や発揮に参加できない人が生じることを指します。自らの社会的地位や特権がマイノリティーの抑圧によって維持されている人達が、そのマイノリティーの声を聞くことで不都合が生じないよう、無知であり続けようとしていると考えられています。選択的夫婦別姓を認めようとしない人々は、正しくマンスプレイニングの状態にあると言えます。
コミュニケーションの問題は、男女格差やマイノリティーへの抑圧、障害に対する偏見、社会にある不平等と排除にも通じています。障害の存在を無視されることにも、マンスプレイニングのような構造があります。障害のある人もない人もともに学ぶインクルーシブ教育を経験できる機会は、日本では限られています。子どもの時から日常的に接する機会が増えれば、接し方も変わります。一律に健常者より下に見る社会構造を変える必要があります。
(2024年6月9日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)